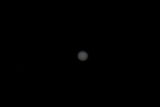30年ほど前に買ったMeadeの10インチ天体望遠鏡の焦点距離が2400mmです。木星や土星などの惑星観察に使っていました。もちろん、アイピースで拡大して観察しますが、このくらいの焦点距離があると惑星は良く見えました。
今回800mmF6.3に2倍テレコンを付けてDXフォーマットで撮ると、計算上は2400mm相当となります。昔使っていた望遠鏡と同じなので、普通に惑星も写るはずです。天体撮影にチャレンジしてみました。
このページの内容は、あくまでも800mmF6.3+2倍テレコン+DXフォーマットで2400mm相当になった時の手ブレ補正効果を確認するための実験です。惑星を撮影するために適した方法ではありません。赤道儀も三脚も使わず、純粋に手持ちで惑星がどこまで写せるのかを検証したものです。
惑星を撮影するのが目的であれば、赤道儀に乗せた望遠鏡のセットをおすすめします。
撮影条件
テストパターンや野鳥撮影で手ブレ補正が大変よく効くことが判明しましたので、星も問題ないはずです。動かないので被写体ブレもなく、野鳥よりもかえって簡単に写るでしょう。手持ち撮影にこだわっているので、天体写真も完全手持ちで撮影してみました。
作例
木星
- ボディ:Z9(Ver. 2.11)
- レンズ:NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S
- テレコンバーター:Z TELECONVERTER TC-2.0X
- 露出:マニュアル
- フォーカス:マニュアル
- 撮影:手持ち撮影(VR ノーマル)
- 画像コンポジット:Registax 6

Exposure Time : 1/320
F Number : 6.3
Exposure Program : Manual
ISO : 100
1280×1280ピクセルの切り出し。
そのままでもDXフォーマットなので1200mm相当の画角になります。21枚の画像をコンポジットしています。惑星は点光源ではなく、このくらいの焦点距離になると面積に写ります。2本の太いバンドも明瞭に写っています。

Exposure Time : 1/160
F Number : 13.0
Exposure Program : Manual
ISO : 100
1280×1280ピクセルの切り出し。
換算2400mm相当の画角になります。2400mm手持ちだとファインダーに入れるのも難しく、さらに連写するとVRノーマルだとセンタリングのためにすぐにファインダーから外れてしまい、撮影は大変困難です。それでも何とか撮影して、57枚の画像をスタックしました。 RegistaxでWavelet処理も行っています。
何とか写る程度ですが、Z9(DXフォーマット)+800mmF6.3+テレコン2Xのシステムで、木星は手持ちで写ります。シーイングがあまり良くなく、望遠鏡に例えると口径10㎝ほどしかないので、それなりの分解能ですが、望遠鏡と違って三脚や赤道儀を用意する必要がなく、手持ちで気軽に撮影できることがメリットです。
このレベルであれば、大赤斑も写るか。今度正中時刻を調べてチャレンジしてみます。
土星

写りました。
月
DXフォーマット2400mm相当で月を撮ると、撮像エリアの短辺にほぼいっぱいに月が写ります。公転軌道が楕円なので、スーパームーンでははみ出すかもしれません。そのくらいの拡大率になります。
- ボディ:Z9(Ver. 2.11)DXフォーマット
- レンズ:NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S
- テレコンバーター:Z TELECONVERTER TC-2.0X
- 露出:マニュアル
- フォーカス:マニュアル
- 撮影:手持ち撮影(VR ノーマル)
- 画像コンポジット:なし

Exposure Time : 1/320
F Number : 13.0
Exposure Program : Manual
ISO : 100
月は極めて明るいので、F13でも低感度のまま高速シャッターが切れます。普通に手持ちで誰でも撮れるでしょう。
月面は白飛びしやすいので、アンダー目に露出補正することをおすすめします。特に南部の大型のクレーター、ティコの内部は反射率が高く、光条も白飛びしやすいので注意が必要です。


追記
このページの内容は、Z9と800mm+2倍テレコンを使って「手持ち」でどこまで撮影できるかをテストしたものです。800mmF6.3の性能評価でもなく、また、こんな方法で惑星や衛星の撮影を推奨するものでもありません。最新のカメラのVRの性能評価の例として個人的な興味本位で行った実験です。
惑星の写真を撮影するのが目的であれば、より安価な望遠鏡システムで引き伸ばし法などで撮影することをおすすめします。




| Amazon Link |
|---|

Nikon Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18d Amazon |

Nikon バッテリー室カバー BL-7 Amazon |

Nikon FTZ II Amazon |

SmallRig ニコンZ9用Lブラケット(ARCA SWISS互換) Amazon |

グラマスGRAMAS Extra Camera Glass Nikon Z 9用 DCG-NI17 クリア Amazon |
おすすめ

NIKKOR Z 24-120mm f/4 S Amazon |

NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 Amazon |

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S Amazon |

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S Amazon |

NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 Amazon |

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S Amazon |

NIKKOR Z 14-30mm f/4S Amazon |

NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 Amazon |

NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 Amazon |

NIKKOR Z 20mm f/1.8 S Amazon |

NIKKOR Z 50mm f/1.2S Amazon |

NIKKOR Z 85mm f/1.2S Amazon |

NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S Amazon |

NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena Amazon |

NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S Amazon |

NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S Amazon |

NIKKOR Z 600/6.3 VR S Amazon |

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S Amazon |

Z TELECONVERTER TC-1.4 Amazon |

Z TELECONVERTER TC-2.0 Amazon |

AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR Amazon |

ニコン マウントアダプターFTZII Amazon |