前回、800mmF6.3と2倍テレコンの組み合わせで木星を手持ち撮影したところ、バンドが結構明瞭に写っていたので、大赤斑も写る確信が得られました。
我が家から見て、木星の高度が高くなる時刻で、大赤斑が正中する時刻の組み合わせで丁度良さそうなのが、9月26日23時49分でした。
機材
- Nikon Z9 (Ver. 2.11)
- NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S
- Z TELECONVERTER TC-2.0X
設定
あくまで「手持ちで木星の大赤斑が写るか」がテーマなので、三脚や赤道儀は使わず、完全手持ちです。
- 撮影モード:マニュアル
- ISO感度:マニュアル(200)
- フォーカス:マニュアルフォーカス
- 連写モード:H(20コマ/秒)
- 手ブレ補正:ノーマル
- フォーマット:DX
撮影
800mmF6.3に2倍テレコンを付けてDXフォーマットで撮ると、2400mmの画角となります。
2400mm相当の光学系だと、まず星を導入するだけで苦労します。
最初から撮影する露光量の設定だと暗くて見えないので、導入時はシャッター速度を遅くして露出オーバー状態で導入すると楽です。導入したらすぐに実撮影のシャッター速度にします。絞りは開放のままです。
その状態を維持したままマニュアルでフォーカスを合わせます。そんなことをしているうちにファインダーから外れてやり直すことを何度か繰り返して、何とかファインダーに取り込めた状態でピントも合い、シャッター速度も調整できたら、後は鬼のように連写します。ファインダーで覗いてできるだけ中央にキープしながら100枚くらい連写すると良いでしょう。
大赤斑正中時刻はSky & Telescopeのサイトから算出しました。日付を入力するとその前後で大赤斑が正中(地球の方に向く)する時刻を計算して教えてくれます。大変便利です。しかも、かなり正確です。
木星の自転は10時間程度なので、見える側の面を通過するのが約5時間。あまり端だと見えないし、カッコ悪いので、正中予想時刻の±1時間前後がよろしいかと思います。ド正中も悪くはありませんが、ちょっと正中から外れていた方が自然な感じだと思います。
処理
天文フリークには今や常識となっているスタッキングを行います。複数の画像を重ね合わせる技術はフィルムの頃からありました。同じ被写体を何枚も撮り、フィルムを重ねて焼き付けると高精細でコントラストが良い画像が得られます。しかし、フィルムの時代はフィルムの厚みが問題となり、かつフィルムのベースも色が付いているため、現実的には数枚のコンポジットしかできませんでした。
デジタルの時代になると、何枚重ねても問題がないので、数十枚、数百枚、数千枚の画像を重ねて1枚の画像を作る方法が主流となりました。連写した静止画を重ねても良いし、動画を撮影して数千枚のフレームを重ねると、元の画像よりも高解像度の画像を得ることができます。
今回は数十枚の静止画像を手持ちで撮影し、Registax(Ver. 6)というソフトでスタッキング処理後、軽くWavelet変換処理をしました。
その後、Photoshopにてコントラストの調整なども行っています。
作例
台風一過で丁度良く晴れてくれましたが、恒星は激しく瞬いていたので、シーイングは良くありません。
単に興味本位で「手持ちハチロクサン+2倍テレコンで木星の大赤斑が写るか」というテーマでチャレンジしてみましたが、拍子抜けするくらいあっけなく写ってしまいました。もちろん、望遠鏡できちんと撮影した映像には到底かないませんが、とりあえず自宅の庭で適当に木星を連写してちょこっと処理すれば大赤斑は写ります。
ただし、木星の写真としては相当ひどいもので、この程度であれば、NikonのコンデジP1000でも撮れると思います。

F Number : 13.0
Exposure Program : Manual
ISO : 200
Date/Time Original : 2022:09:26 23:35:07
DXフォーマットで撮影した元画像の中央部1280×1280ドットのエリアを切り出し。
こんな画像を70枚撮影。


なじみのある木星の顔は、大赤斑が上にある写真ですが、望遠鏡の写真は上下左右逆さに写るからです。本来は南半球にあるので、望遠レンズで写すとこのように下に写ります。
掩蔽直前のエウロパ(木星の右肩に接する衛星)とイオ(右にちょっと離れた衛星)も写っています。
近年、南側のベルト(南赤道縞)が薄くなっていますが、かえってその方が大赤斑が目立ちます。大赤斑正中の30分ほど前を狙いました。
あまり高解像ではありませんが、大赤斑は十分認識できます。シーイングが良い日にもう少しこだわればもっと高精細の画像が撮れると思います。
色もあまり出ていません。ベルトも大赤斑ももう少し赤みがかって欲しいところですが、どこかの段階で彩度がずいぶん落ちてしまったようです。 いつか時間があるときに再度チャレンジしてみようと思います。
追記
このページの内容は、Z9と800mm+2倍テレコンを使って「手持ち」でどこまで撮影できるかをテストしたものです。800mmF6.3の性能評価でもなく、また、こんな方法で惑星や衛星の撮影を推奨するものでもありません。最新のカメラのVRの性能評価の例として個人的な興味本位で行った実験です。
惑星の写真を撮影するのが目的であれば、より安価な望遠鏡システムで引き伸ばし法などで撮影することをおすすめします。




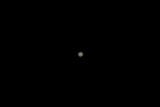


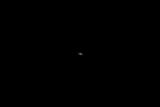
| Amazon Link |
|---|

Nikon Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18d Amazon |

Nikon バッテリー室カバー BL-7 Amazon |

Nikon FTZ II Amazon |

SmallRig ニコンZ9用Lブラケット(ARCA SWISS互換) Amazon |

グラマスGRAMAS Extra Camera Glass Nikon Z 9用 DCG-NI17 クリア Amazon |
おすすめ

NIKKOR Z 24-120mm f/4 S Amazon |

NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 Amazon |

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S Amazon |

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S Amazon |

NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 Amazon |

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S Amazon |

NIKKOR Z 14-30mm f/4S Amazon |

NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 Amazon |

NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 Amazon |

NIKKOR Z 20mm f/1.8 S Amazon |

NIKKOR Z 50mm f/1.2S Amazon |

NIKKOR Z 85mm f/1.2S Amazon |

NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S Amazon |

NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena Amazon |

NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S Amazon |

NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S Amazon |

NIKKOR Z 600/6.3 VR S Amazon |

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S Amazon |

Z TELECONVERTER TC-1.4 Amazon |

Z TELECONVERTER TC-2.0 Amazon |

AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR Amazon |

ニコン マウントアダプターFTZII Amazon |











